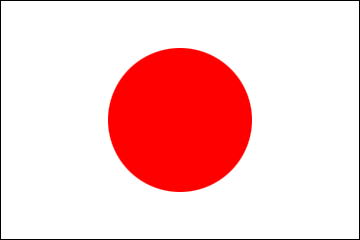当館の戸籍・国籍関係届出手続き
令和7年6月4日
戸籍・国籍の届出は、開館日の領事窓口時間のうち、8時00分~13時00分、14時00分~15時30分の間にお願いします。
1.海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、全て戸籍に記載されることになっています。
2.戸籍関係の届出は、大使館等在外公館の他、日本の本籍地役場でも行うことができます。当館を含む在外公館で届出をされた場合、届出の事項が戸籍に反映されるまで2か月程度を要します。戸籍への記載を急ぐ場合は、本籍地の役場に事前に必要書類等を確認の上、直接、届出を提出してください(日本の本籍地に届け出る場合は、必要書類が異なることがあります。)。
3.在外公館で受付・受理できる届出は、以下に案内する届出以外にもあります。在外公館に提出できる届出については領事班に照会願います。
●戸籍・国籍関係届の届出について(外務省ウェブサイト)
●えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(外務省ウェブサイト)
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
【届出条件】
ア 当事者双方が日本人であること
イ 当事者間に婚姻について合意があること
ウ 婚姻年齢(男性・女性ともに18歳)に達していること(注)
エ 重婚ではないこと
オ 女性が令和6年3月31日以前に再婚した場合、再婚禁止期間が終了していること(※令和6年4月1日以降の婚姻については、女性に対する待婚期間は廃止。)
カ 当事者双方の関係が法定の近親者でないこと
(注)令和4年(2022年)4月1日から女性の婚姻年齢が18歳に引き上げられ、婚姻年齢は男女共に18歳になりました。なお、令和4年(2022年)4月1日の時点で既に16歳以上の女性は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。その場合には、未成年者の保護者の同意が必要となります。詳しくはこちらをご確認ください。
【届出人】
当事者双方
【必要書類】
ア 婚姻届(届書は領事窓口にも準備しています。)(記載見本):2通
※1~2ページを全て記入してください。印刷する場合はA4サイズ2枚またはA3サイズ1枚で印刷してください。
※成人の証人2名の署名、捺印(印鑑がない場合は拇印)が必要です。外国人が証人になることも可能です。
※2通目は、1通目の署名以外の部分をコピーし、署名したものでも可。
イ 届出人を確認する写真付きの身分証明書(パスポート等)の提示及びその写し:各1通
ウ 当事者双方の戸籍謄(抄)本:原則として戸籍謄本の添付は不要(※ただし、本籍地において戸籍情報が電算化されていない方については、戸籍謄本の提出が必要となります。その場合の提出部数は、原本1通、写し1通になります。)
【届出条件】
ア 外国の法律に基づいて婚姻が成立していること
イ 当事者の一方が日本人であること
【届出人】
日本人当事者(※外国人当事者が届け出ることもできますが、届出内容に確認事項や修正がある場合には窓口で対応いただく必要がありますので、日本国籍者の当事者が届出されるようお願いします。)
【必要書類】
(1)婚姻届(記載見本):2通
※1ページ目のみ記入し、印刷する場合は1ページ目のみをA4サイズで印刷してください。届書は領事窓口にも準備しています。
※2通目は、1通目の署名以外の部分をコピーし、署名したものでも可。
(2)届出人を確認できる写真付きの身分証明書(パスポート等)の提示及びその写し:1通
(3)戸籍謄(抄)本:原則として戸籍謄本の添付は不要(※ただし、本籍地において戸籍情報が電算化されていない方については、戸籍謄本の提出が必要となります。その場合の提出部数は、原本1通、写し1通になります。)
(4)外国籍配偶者のパスポートの提示及びパスポートの身分事項ページの写し:2通(※パスポートがない場合は出生証明書:原本1通、写し1通)
(5)上記(4)の日本語翻訳文:2通
※届出人等が翻訳する場合、文末に翻訳者氏名を明記してください。
(6)婚姻証明書:原本1通、写し1通(電子証明書の取扱い)
(7)上記(6)の日本語翻訳文:2通(日本語翻訳文参考例)
※届出人等が翻訳する場合、文末に翻訳者氏名を明記してください。
【届出期間】
婚姻成立日から3か月以内
※届出期間を過ぎても届出することができます。その場合には、上記必要書類の他、「遅延理由書」(様式任意)2通(原本1通、写し1通)を提出してください。
【届出人】
外国人と婚姻し、その者の氏を称しようとする者
【届出期間】
婚姻成立後6か月以内(※婚姻届と同時に届出できます。婚姻成立後6か月を過ぎた後に変更する場合は日本の家庭裁判所の許可が必要になり、日本国外での届出はできませんのでご注意ください。)
【必要書類】
※婚姻届と当時に届出する場合、提出に必要な書類で婚姻届と重複するものは省略できます。
(1)外国人との婚姻による氏の変更届出書:2通(記載見本)
※印刷する場合はA4サイズで印刷してください。届書は領事窓口にも準備しています。
※2通目は、1通目の署名以外の部分をコピーし、署名したものでも可。
(2)届出人を確認できる写真付きの身分証明書(パスポート等)の提示及びその写し:1通
(3)婚姻の事実が確認できる戸籍謄(抄)本:原則として戸籍謄本の添付は不要(※ただし、本籍地において戸籍情報が電算化されていない方については、戸籍謄本の提出が必要となります。その場合の提出部数は、原本1通、写し1通になります。)
(4)外国籍配偶者のパスポートの提示及び身分事項ページの写し:2通(※パスポートがない場合は出生証明書:原本1通、写し1通)
(5)上記(4)の日本語翻訳文:2通
※届出人等が翻訳する場合、文末に翻訳者氏名を明記してください。
(6)婚姻証明書:原本1通、写し1通(電子証明書の取扱い)
(7)上記(6)の日本語翻訳文:2通(日本語翻訳文参考例)
※届出人等が翻訳する場合、文末に翻訳者氏名を明記してください。
【届出条件】
以下のいずれかに当てはまる子
(1)婚姻関係にある父母の両方もしくは一方が日本国籍者の子
(2)日本国籍者の母の子
(3)日本国籍者の父から胎児認知を受けている子
【届出人】
(1)上記届出条件(1)の場合は、父または母(※届出内容に確認事項や修正がある場合には窓口で対応いただく必要がありますので、日本国籍者の父または母が届出されるようお願いします。)
(2)上記届出条件(2)及び(3)の場合は、母
【届出期間】
日本国外で出生した場合、出生の日を含めて3か月以内(例:1月23日に出生した場合、4月22日までに出生届を提出。)
※戸籍法第49条により「出生の届出は,14日以内(国外で出生したときは,3か月以内)にこれをしなければならない」と定められています。また、国籍法第12条により「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意志を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う」と定められています。日本国外で出生した日本国民で、出生により外国籍を取得した場合、この届出期限を過ぎる前に日本国籍を留保する意志を表示して出生の届出をしなければ、日本国籍を失いますのでご注意ください。
【必要書類】
ア 出生届:2通(記載見本)
※1ページ目のみ記入し、印刷する場合は1ページ目のみ、A4サイズで印刷してください。届書は領事窓口にも準備しています。
※2通目は、1通目の署名以外の部分をコピー、署名したものでも可。
【提出部数についての注意事項】新たに本籍を設ける場合(父母のいずれかが戸籍の筆頭者でない場合や胎児認知された子の場合等)で、父母の現在の本籍地と違う市区町村に新たな本籍を設ける場合は、出生届を始めとする必要書類は各3通(原本1通、写し2通)必要です。
※出生届の「生まれたところ」には、出生した病院の住所を記入してください。病院の住所は、各病院の公式ウェブサイトに掲載されているものを記入願います。
(病院参考)
・Abdali Hospital: https://www.abdalihospital.com/home
・Shmaisani Hospital: http://shamisani-hospital.com/
・Al-Hayat General Hospital: http://www.alhayathos.net/Default.aspx?Lng=2&P=CU&Q=5
イ 届出人を確認できる写真付きの身分証明書(パスポート等)の提示及びその写し:1通
ウ 出生証明書(ヨルダン内務省発行):届書と同部数(※原本1通以外は写しで可。)(電子証明書の取扱い)
エ 上記ウの日本語翻訳文:届書と同部数(日本語翻訳文参考例)
※ 届出人等が翻訳する場合は、文末に翻訳者氏名を明記してください。
オ 申述書:届書と同部数
※ヨルダンの出生証明書には出生時間の記載がないので、申述書で出生時間を明記していただく必要があります。
カ (子が嫡出でない場合)父親の氏名、生年月日及び国籍が分かる身分証明書(パスポート等)の提示とその写し:届書と同部数
キ (※届出の記載事項を確認するのに必要ですので、手元にある場合には必ずお持ちください)戸籍謄本の写し:1部
【注意事項】
出生届を当館に提出した場合、戸籍への反映に2か月程度かかります。新生児の日本のパスポートの申請を行う場合、戸籍謄本、または戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間内のもの)が必要になります。詳しくは、パスポート(旅券)のページをご確認ください。
【届出条件】
死亡した者が日本人であること
※外国人配偶者の死亡を戸籍に反映させるためには、以下の「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」をご確認ください。
【届出人】
死亡届は以下の順に届出の義務がありますが、順位に関係なく届出することが可能です。(※届出内容に確認事項や修正がある場合には窓口で対応いただく必要がありますので、日本国籍者の方が届出または届出人に同伴されるようお願いします。)
(1)同居の親族
(2)その他の同居者
(3)家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
同居していない親族、後見人、補佐人、補助人及び任意後見人は届出の義務はありませんが、届出をすることができます。
【届出期間】
死亡の事実を知った日から3か月以内
【必要書類】
(1)死亡届:2通(記載見本)
※1ページ目のみ記入し、印刷する場合は1ページ目のみをA4サイズで印刷してください。届書は領事窓口にも準備しています。
※2通目は、1通目の署名以外の部分をコピー、署名したものでも可。
(2)届出人を確認する写真付きの身分証明書(パスポート等)の提示及びその写し:1通
(3)死亡証明書(ヨルダン内務省発行):原本1通、写し1通(電子証明書の取扱い)
(4)日本語翻訳文:2通(※ 届出人等が翻訳する場合は、文末に翻訳者氏名を明記してくだ さい。)
(5)(※届出の記載事項を確認するのに必要ですので、手元にある場合には必ずお持ちください)戸籍謄(抄)本の写し:1通
(6)申述書:2通
※ ヨルダンの死亡証明書には、死亡時間が実際のものではなく、00時00分と記載される場合があります。この場合、申述書にて実際の死亡時分を明記する必要があります(※外国語で記入された申述書は、日本語翻訳文が必要です。)。
(7)亡くなった方の日本国旅券(※失効処理をして返却します。)
(8)遅延理由書(※死亡の事実を知った日から3か月以上経過した場合):2通(※外国語で記載されたものは、日本語翻訳文が2通必要です。)
【注意事項】
ご遺体またはご遺骨を日本に移送され、日本での火葬または埋葬を希望する場合には、日本の市区町村役場から火葬または埋葬の許可を得る必要があります。この許可は、市区町村での死亡届の受理又は、戸籍への死亡事実の記載があることが条件となっています。当館を含む在外公館で死亡届を受理した場合、届出書は外務省を経由し本籍地役場へ送付されるため、本籍地役場へ届出書が到着するまで1か月半程度の時間を要しますので、日本での埋葬(または火葬)を希望される場合、死亡届は日本の市区町村役場へ直接提出してください。
【届出人】
亡くなった外国人配偶者の日本人配偶者
【届出期間】
死亡の事実を知ってから3か月以内
【必要書類】
(1)婚姻解消事由申出書:2通 (記載見本)
※ 印刷する場合はA4サイズで印刷してください。届書は領事窓口にも届書を準備しています。
※2通目は、1通目の署名以外の部分をコピー、署名したものでも可。
(2)届出人を確認する写真付きの身分証明書(パスポート等)の提示及びその写し:1通
(3)死亡証明書(ヨルダン内務省発行) :原本1通、写し1通(電子証明書の取扱い)
(4)上記(2)の日本語翻訳文:2通 (※届出人等が翻訳する場合、文末に翻訳者氏名を明記してください。)
(5)申述書:2通
※ヨルダンの死亡証明書には、死亡時間が実際のものではなく、00時00分と記載される場合があります。この場合、申述書にて実際の死亡時分を明記する必要があります。
(6)(※戸籍の記載事項を確認するのに必要ですので、手元にある場合には必ずお持ちください)日本人配偶者の戸籍謄本の写し:1通
(7)遅延理由書(※亡くなった事実を知ってから3か月を経過した場合):2通
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、いずれかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本国籍を失うことがありますので注意して下さい。
(注1)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)いずれかの国籍を選択すれば足ります。
(注2)以上の期限を徒過した場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。
国籍選択は重国籍者の大切な義務です(法務省作成リーフレット)
国籍の選択は、自己の意思に基づいて、次のいずれかの方法により行って下さい。
(1)日本国籍を選択する場合
ア 当該外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、離脱を証明する書面を添付し大使館又は本邦の市区町村役場に外国国籍喪失届をして下さい。離脱の手続きについては、当該外国の関係機関に相談して下さい。
イ 日本の国籍の選択を宣言する方法
戸籍謄本を添付して大使館または本邦の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届(届出の方法は、以下をご確認願います。)をして下さい。国籍選択届の詳細については、以下に記載しておりますので、そちらをご確認願います。
(2)外国の国籍を選択する場合で、日本の国籍を離脱する方法及び外国の国籍を選択する方法
以下の外務省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html#section5
●国籍選択届
【届出人】
日本国籍を選択しようとする者が、15歳以上であるときは本人、その者が15歳未満のときは、その法定代理人(親権者等)
【必要書類】
(1)国籍選択届(領事窓口にも準備しています):2通(記載見本)
※印刷する場合はA4サイズで印刷してください。届書は領事窓口にも準備しています。
※2通目は、1通目の署名以外の部分をコピーし、署名したものでも可。
(2)届出人を確認する写真付きの身分証明書(パスポート等)の提示及びその写し:1通
(3) 戸籍謄本: 原則として戸籍謄本の添付は不要(※ただし、本籍地において戸籍情報が電算化されていない方については、戸籍謄本の提出が必要となります。その場合の提出部数は、原本1通、写し1通になります。)
【届出期間】
※以下の選択期限を経過してしまった場合であっても、国籍の選択の届出をする必要があります。
・18歳に達する以前に重国籍となった場合: 20歳に達するまで
・18歳に達した後に重国籍となった場合: 重国籍となった時から2年以内
※ただし,令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り,令和4(2022)年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については,同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
注意事項
1.海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、全て戸籍に記載されることになっています。
2.戸籍関係の届出は、大使館等在外公館の他、日本の本籍地役場でも行うことができます。当館を含む在外公館で届出をされた場合、届出の事項が戸籍に反映されるまで2か月程度を要します。戸籍への記載を急ぐ場合は、本籍地の役場に事前に必要書類等を確認の上、直接、届出を提出してください(日本の本籍地に届け出る場合は、必要書類が異なることがあります。)。
3.在外公館で受付・受理できる届出は、以下に案内する届出以外にもあります。在外公館に提出できる届出については領事班に照会願います。
●戸籍・国籍関係届の届出について(外務省ウェブサイト)
●えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(外務省ウェブサイト)
1. 婚姻届: 日本人同士が日本方式によって婚姻する場合
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
【届出条件】
ア 当事者双方が日本人であること
イ 当事者間に婚姻について合意があること
ウ 婚姻年齢(男性・女性ともに18歳)に達していること(注)
エ 重婚ではないこと
オ 女性が令和6年3月31日以前に再婚した場合、再婚禁止期間が終了していること(※令和6年4月1日以降の婚姻については、女性に対する待婚期間は廃止。)
カ 当事者双方の関係が法定の近親者でないこと
(注)令和4年(2022年)4月1日から女性の婚姻年齢が18歳に引き上げられ、婚姻年齢は男女共に18歳になりました。なお、令和4年(2022年)4月1日の時点で既に16歳以上の女性は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。その場合には、未成年者の保護者の同意が必要となります。詳しくはこちらをご確認ください。
【届出人】
当事者双方
【必要書類】
ア 婚姻届(届書は領事窓口にも準備しています。)(記載見本):2通
※1~2ページを全て記入してください。印刷する場合はA4サイズ2枚またはA3サイズ1枚で印刷してください。
※成人の証人2名の署名、捺印(印鑑がない場合は拇印)が必要です。外国人が証人になることも可能です。
※2通目は、1通目の署名以外の部分をコピーし、署名したものでも可。
イ 届出人を確認する写真付きの身分証明書(パスポート等)の提示及びその写し:各1通
ウ 当事者双方の戸籍謄(抄)本:原則として戸籍謄本の添付は不要(※ただし、本籍地において戸籍情報が電算化されていない方については、戸籍謄本の提出が必要となります。その場合の提出部数は、原本1通、写し1通になります。)
2. 婚姻届: 日本人と外国人が外国方式によって婚姻した場合
【届出条件】
ア 外国の法律に基づいて婚姻が成立していること
イ 当事者の一方が日本人であること
【届出人】
日本人当事者(※外国人当事者が届け出ることもできますが、届出内容に確認事項や修正がある場合には窓口で対応いただく必要がありますので、日本国籍者の当事者が届出されるようお願いします。)
【必要書類】
(1)婚姻届(記載見本):2通
※1ページ目のみ記入し、印刷する場合は1ページ目のみをA4サイズで印刷してください。届書は領事窓口にも準備しています。
※2通目は、1通目の署名以外の部分をコピーし、署名したものでも可。
(2)届出人を確認できる写真付きの身分証明書(パスポート等)の提示及びその写し:1通
(3)戸籍謄(抄)本:原則として戸籍謄本の添付は不要(※ただし、本籍地において戸籍情報が電算化されていない方については、戸籍謄本の提出が必要となります。その場合の提出部数は、原本1通、写し1通になります。)
(4)外国籍配偶者のパスポートの提示及びパスポートの身分事項ページの写し:2通(※パスポートがない場合は出生証明書:原本1通、写し1通)
(5)上記(4)の日本語翻訳文:2通
※届出人等が翻訳する場合、文末に翻訳者氏名を明記してください。
(6)婚姻証明書:原本1通、写し1通(電子証明書の取扱い)
(7)上記(6)の日本語翻訳文:2通(日本語翻訳文参考例)
※届出人等が翻訳する場合、文末に翻訳者氏名を明記してください。
【届出期間】
婚姻成立日から3か月以内
※届出期間を過ぎても届出することができます。その場合には、上記必要書類の他、「遅延理由書」(様式任意)2通(原本1通、写し1通)を提出してください。
3. 外国人との婚姻による氏の変更届
【届出人】
外国人と婚姻し、その者の氏を称しようとする者
【届出期間】
婚姻成立後6か月以内(※婚姻届と同時に届出できます。婚姻成立後6か月を過ぎた後に変更する場合は日本の家庭裁判所の許可が必要になり、日本国外での届出はできませんのでご注意ください。)
【必要書類】
※婚姻届と当時に届出する場合、提出に必要な書類で婚姻届と重複するものは省略できます。
(1)外国人との婚姻による氏の変更届出書:2通(記載見本)
※印刷する場合はA4サイズで印刷してください。届書は領事窓口にも準備しています。
※2通目は、1通目の署名以外の部分をコピーし、署名したものでも可。
(2)届出人を確認できる写真付きの身分証明書(パスポート等)の提示及びその写し:1通
(3)婚姻の事実が確認できる戸籍謄(抄)本:原則として戸籍謄本の添付は不要(※ただし、本籍地において戸籍情報が電算化されていない方については、戸籍謄本の提出が必要となります。その場合の提出部数は、原本1通、写し1通になります。)
(4)外国籍配偶者のパスポートの提示及び身分事項ページの写し:2通(※パスポートがない場合は出生証明書:原本1通、写し1通)
(5)上記(4)の日本語翻訳文:2通
※届出人等が翻訳する場合、文末に翻訳者氏名を明記してください。
(6)婚姻証明書:原本1通、写し1通(電子証明書の取扱い)
(7)上記(6)の日本語翻訳文:2通(日本語翻訳文参考例)
※届出人等が翻訳する場合、文末に翻訳者氏名を明記してください。
4. 出生届
【届出条件】
以下のいずれかに当てはまる子
(1)婚姻関係にある父母の両方もしくは一方が日本国籍者の子
(2)日本国籍者の母の子
(3)日本国籍者の父から胎児認知を受けている子
【届出人】
(1)上記届出条件(1)の場合は、父または母(※届出内容に確認事項や修正がある場合には窓口で対応いただく必要がありますので、日本国籍者の父または母が届出されるようお願いします。)
(2)上記届出条件(2)及び(3)の場合は、母
【届出期間】
日本国外で出生した場合、出生の日を含めて3か月以内(例:1月23日に出生した場合、4月22日までに出生届を提出。)
※戸籍法第49条により「出生の届出は,14日以内(国外で出生したときは,3か月以内)にこれをしなければならない」と定められています。また、国籍法第12条により「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意志を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う」と定められています。日本国外で出生した日本国民で、出生により外国籍を取得した場合、この届出期限を過ぎる前に日本国籍を留保する意志を表示して出生の届出をしなければ、日本国籍を失いますのでご注意ください。
【必要書類】
ア 出生届:2通(記載見本)
※1ページ目のみ記入し、印刷する場合は1ページ目のみ、A4サイズで印刷してください。届書は領事窓口にも準備しています。
※2通目は、1通目の署名以外の部分をコピー、署名したものでも可。
【提出部数についての注意事項】新たに本籍を設ける場合(父母のいずれかが戸籍の筆頭者でない場合や胎児認知された子の場合等)で、父母の現在の本籍地と違う市区町村に新たな本籍を設ける場合は、出生届を始めとする必要書類は各3通(原本1通、写し2通)必要です。
※出生届の「生まれたところ」には、出生した病院の住所を記入してください。病院の住所は、各病院の公式ウェブサイトに掲載されているものを記入願います。
(病院参考)
・Abdali Hospital: https://www.abdalihospital.com/home
・Shmaisani Hospital: http://shamisani-hospital.com/
・Al-Hayat General Hospital: http://www.alhayathos.net/Default.aspx?Lng=2&P=CU&Q=5
イ 届出人を確認できる写真付きの身分証明書(パスポート等)の提示及びその写し:1通
ウ 出生証明書(ヨルダン内務省発行):届書と同部数(※原本1通以外は写しで可。)(電子証明書の取扱い)
エ 上記ウの日本語翻訳文:届書と同部数(日本語翻訳文参考例)
※ 届出人等が翻訳する場合は、文末に翻訳者氏名を明記してください。
オ 申述書:届書と同部数
※ヨルダンの出生証明書には出生時間の記載がないので、申述書で出生時間を明記していただく必要があります。
カ (子が嫡出でない場合)父親の氏名、生年月日及び国籍が分かる身分証明書(パスポート等)の提示とその写し:届書と同部数
キ (※届出の記載事項を確認するのに必要ですので、手元にある場合には必ずお持ちください)戸籍謄本の写し:1部
【注意事項】
出生届を当館に提出した場合、戸籍への反映に2か月程度かかります。新生児の日本のパスポートの申請を行う場合、戸籍謄本、または戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間内のもの)が必要になります。詳しくは、パスポート(旅券)のページをご確認ください。
5. 死亡届
【届出条件】
死亡した者が日本人であること
※外国人配偶者の死亡を戸籍に反映させるためには、以下の「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」をご確認ください。
【届出人】
死亡届は以下の順に届出の義務がありますが、順位に関係なく届出することが可能です。(※届出内容に確認事項や修正がある場合には窓口で対応いただく必要がありますので、日本国籍者の方が届出または届出人に同伴されるようお願いします。)
(1)同居の親族
(2)その他の同居者
(3)家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
同居していない親族、後見人、補佐人、補助人及び任意後見人は届出の義務はありませんが、届出をすることができます。
【届出期間】
死亡の事実を知った日から3か月以内
【必要書類】
(1)死亡届:2通(記載見本)
※1ページ目のみ記入し、印刷する場合は1ページ目のみをA4サイズで印刷してください。届書は領事窓口にも準備しています。
※2通目は、1通目の署名以外の部分をコピー、署名したものでも可。
(2)届出人を確認する写真付きの身分証明書(パスポート等)の提示及びその写し:1通
(3)死亡証明書(ヨルダン内務省発行):原本1通、写し1通(電子証明書の取扱い)
(4)日本語翻訳文:2通(※ 届出人等が翻訳する場合は、文末に翻訳者氏名を明記してくだ さい。)
(5)(※届出の記載事項を確認するのに必要ですので、手元にある場合には必ずお持ちください)戸籍謄(抄)本の写し:1通
(6)申述書:2通
※ ヨルダンの死亡証明書には、死亡時間が実際のものではなく、00時00分と記載される場合があります。この場合、申述書にて実際の死亡時分を明記する必要があります(※外国語で記入された申述書は、日本語翻訳文が必要です。)。
(7)亡くなった方の日本国旅券(※失効処理をして返却します。)
(8)遅延理由書(※死亡の事実を知った日から3か月以上経過した場合):2通(※外国語で記載されたものは、日本語翻訳文が2通必要です。)
【注意事項】
ご遺体またはご遺骨を日本に移送され、日本での火葬または埋葬を希望する場合には、日本の市区町村役場から火葬または埋葬の許可を得る必要があります。この許可は、市区町村での死亡届の受理又は、戸籍への死亡事実の記載があることが条件となっています。当館を含む在外公館で死亡届を受理した場合、届出書は外務省を経由し本籍地役場へ送付されるため、本籍地役場へ届出書が到着するまで1か月半程度の時間を要しますので、日本での埋葬(または火葬)を希望される場合、死亡届は日本の市区町村役場へ直接提出してください。
6. 婚姻解消事由申出書
【届出人】
亡くなった外国人配偶者の日本人配偶者
【届出期間】
死亡の事実を知ってから3か月以内
【必要書類】
(1)婚姻解消事由申出書:2通 (記載見本)
※ 印刷する場合はA4サイズで印刷してください。届書は領事窓口にも届書を準備しています。
※2通目は、1通目の署名以外の部分をコピー、署名したものでも可。
(2)届出人を確認する写真付きの身分証明書(パスポート等)の提示及びその写し:1通
(3)死亡証明書(ヨルダン内務省発行) :原本1通、写し1通(電子証明書の取扱い)
(4)上記(2)の日本語翻訳文:2通 (※届出人等が翻訳する場合、文末に翻訳者氏名を明記してください。)
(5)申述書:2通
※ヨルダンの死亡証明書には、死亡時間が実際のものではなく、00時00分と記載される場合があります。この場合、申述書にて実際の死亡時分を明記する必要があります。
(6)(※戸籍の記載事項を確認するのに必要ですので、手元にある場合には必ずお持ちください)日本人配偶者の戸籍謄本の写し:1通
(7)遅延理由書(※亡くなった事実を知ってから3か月を経過した場合):2通
7. 国籍選択届等
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、いずれかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本国籍を失うことがありますので注意して下さい。
(注1)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)いずれかの国籍を選択すれば足ります。
(注2)以上の期限を徒過した場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。
国籍選択は重国籍者の大切な義務です(法務省作成リーフレット)
国籍の選択は、自己の意思に基づいて、次のいずれかの方法により行って下さい。
(1)日本国籍を選択する場合
ア 当該外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、離脱を証明する書面を添付し大使館又は本邦の市区町村役場に外国国籍喪失届をして下さい。離脱の手続きについては、当該外国の関係機関に相談して下さい。
イ 日本の国籍の選択を宣言する方法
戸籍謄本を添付して大使館または本邦の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届(届出の方法は、以下をご確認願います。)をして下さい。国籍選択届の詳細については、以下に記載しておりますので、そちらをご確認願います。
(2)外国の国籍を選択する場合で、日本の国籍を離脱する方法及び外国の国籍を選択する方法
以下の外務省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html#section5
●国籍選択届
【届出人】
日本国籍を選択しようとする者が、15歳以上であるときは本人、その者が15歳未満のときは、その法定代理人(親権者等)
【必要書類】
(1)国籍選択届(領事窓口にも準備しています):2通(記載見本)
※印刷する場合はA4サイズで印刷してください。届書は領事窓口にも準備しています。
※2通目は、1通目の署名以外の部分をコピーし、署名したものでも可。
(2)届出人を確認する写真付きの身分証明書(パスポート等)の提示及びその写し:1通
(3) 戸籍謄本: 原則として戸籍謄本の添付は不要(※ただし、本籍地において戸籍情報が電算化されていない方については、戸籍謄本の提出が必要となります。その場合の提出部数は、原本1通、写し1通になります。)
【届出期間】
※以下の選択期限を経過してしまった場合であっても、国籍の選択の届出をする必要があります。
・18歳に達する以前に重国籍となった場合: 20歳に達するまで
・18歳に達した後に重国籍となった場合: 重国籍となった時から2年以内
※ただし,令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り,令和4(2022)年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については,同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。